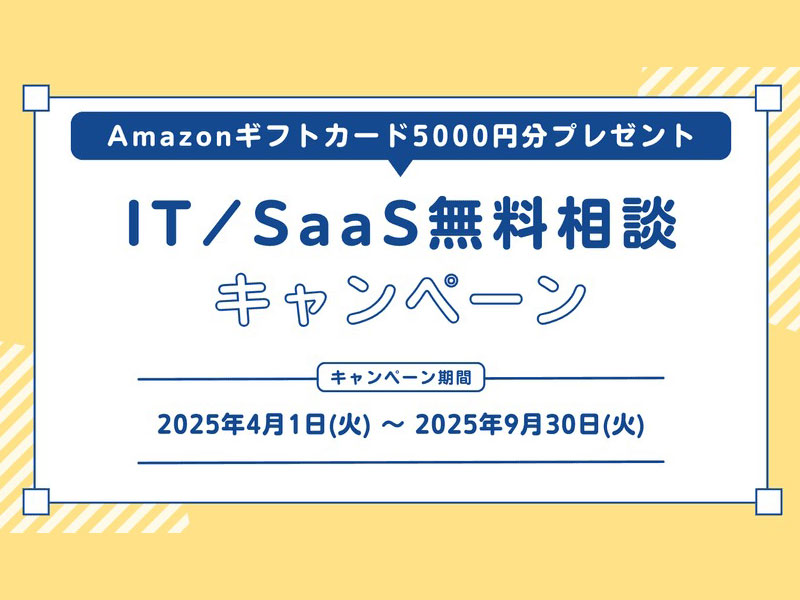- ITmedia ビジネスオンライン
- 今の日本は「人員不足」時代――人材使い捨てと単なる安売りはもう...
今の日本は「人員不足」時代――人材使い捨てと単なる安売りはもう通用しない:INSIGHT NOW!(1/3 ページ)
著者プロフィール:日沖博道(ひおき・ひろみち)
パスファインダーズ社長。25年にわたる戦略・業務・ITコンサルティングの経験と実績を基に「空回りしない」業務改革/IT改革を支援。アビームコンサルティング、日本ユニシス、アーサー・D・リトル、松下電送出身。一橋大学経済学部卒。日本工業大学 専門職大学院(MOTコース)客員教授(2008年~)。今季講座:「ビジネスモデル開発とリエンジニアリング」。
最近、さまざまな業界で人手不足が表面化している。デフレ時代には若い人材を安くこき使うしか能のない企業がのさばっていたが、これからは違う。その変化は、もうアルバイト採用で始まっている。
人手不足といえば、景気低迷期からずっと介護業界が指摘されてきたが、これは資格が必要で仕事内容が大変な割に給与が低いためだ。そして、その事態は今でも変わっていない(これは制度設計から変革する必要がありそうだが)。
その後、東日本大震災後の復興事業と、復活した自民党が推す「国土強靭化」が合わせ技として効くようになったタイミングからは、建設資材の高騰とともに、建設作業者が全国で急速に不足するようになった。この事態については、過去にも何度か指摘したが、スキルや経験が必要なものが多く、もともと限られた供給がボトルネックになっている。
外食業界では閉店に追い込まれるケースも
近ごろは、外食業界でも人手不足が深刻だ。アルバイトが集まらないため、営業時間を短くしたり、店舗新設を断念したりする外食チェーンが続出しており、中には閉店を余儀なくされる事例も出てきた。元来、店舗数を増やすことで成長するのが定石の業界なので、かなり切羽詰まった事態だといえる(参考リンク)。
こちらは特別なスキルを要求するわけではなく、ごく普通のアルバイト人員を求めているのだが、介護業界と並ぶ労働条件の悪さのため、採用に大苦戦するようになっている。外食業界での人手不足は恒常的なものがあり、デフレ真っただ中の時期でも、辞めていく人を補充するために1年じゅう「アルバイト募集中」の張り紙をしているチェーン店が多かったのが実態だ。景気が少し良くなって、コンビニなど他業界にアルバイト希望者が流れるようになったことも背景にある。
個々の店では不足する人手が補充されないため、残ったスタッフにさらに重い負荷がかかるようになり、やがて彼らが体や精神を壊して脱落するという“悪循環”に陥る店も少なくない。その労働環境の苛酷さが表面化して「ブラック企業」の悪評が立ったチェーン店は(今まさに大騒ぎになっている店だが)、当然だが採用に苦しむケースが余計に多く、こうした悪循環も酷かったという。
しかし、これはごく一部の外食チェーン店に限る話でもなく、かなり多くの外食店、そして小売や物流・倉庫業など「体力勝負」の業界に共通する悩みのようだ。特に低価格をウリにして伸びてきた企業ではその傾向が強いといえる。
Copyright (c) INSIGHT NOW! All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング
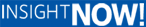
 外食チェーンの「すき屋」。人手不足からか一時閉店した店も少なくない
外食チェーンの「すき屋」。人手不足からか一時閉店した店も少なくない 全国展開する「はなまるうどん」や「丸亀製麺」が福岡で苦戦するワケ
全国展開する「はなまるうどん」や「丸亀製麺」が福岡で苦戦するワケ タイの反政府デモ騒動、両者は何を争っているのか
タイの反政府デモ騒動、両者は何を争っているのか JR北海道が抱える宿唖(しゅくあ)
JR北海道が抱える宿唖(しゅくあ) エアアジア・ジャパン、不振の原因は何だったのか?
エアアジア・ジャパン、不振の原因は何だったのか? 「断れない営業」は組織を滅ぼす
「断れない営業」は組織を滅ぼす