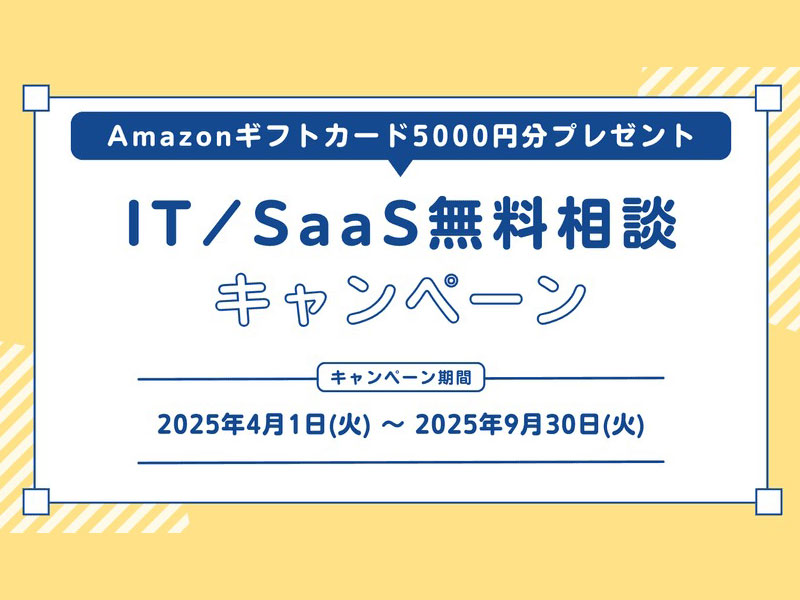- ITmedia ビジネスオンライン
- やはり英語は必要なのか? 日本人にとっての壁:佐々木俊尚×松井...
やはり英語は必要なのか? 日本人にとっての壁:佐々木俊尚×松井博 グローバル化と幸福の怪しい関係(2)(1/5 ページ)
佐々木俊尚×松井博 グローバル化と幸福の怪しい関係:
少子・高齢化に歯止めがかからない日本市場は、「縮小していくのみ」「よくて横ばい」といった見方が強い。企業は沈みゆく市場から抜け出し、グローバル化の中で新たな“財宝”を手にしようとしている。製造拠点を海外に移転したり、海外との取引を増やしたり、社内公用語を英語にしたり――。
こうした一連の動きによって、私たちの働き方はどのように変化していくのだろうか。また企業が巨大化すれば、私たちの生活は充実するのだろうか。この問題について、ITやメディア事情に詳しいジャーナリストの佐々木俊尚さんと、アップルのどん底時代と黄金時代を経験した松井博さんが徹底的に語り合った。全9回でお送りする。
バックナンバー:
もう場所は関係ない
松井:私が『僕がアップルで学んだこと』(アスキー新書)という本を書いたときにGoogle docs(Googleが無料提供する、Webブラウザ内で動くソフト)を使いました。そして編集もすべてGoogle docsでしてもらったんです。つまり、私が米国から執筆しておくと、私が寝ている間に、本が仕上がっていくわけですよ(笑)。このとき思いましたね。「もう場所は関係ないな」と。
アップルにいるときにも海外相手に仕事をしていましたが、あまり実感がありませんでした。しかし今回のように本をつくる作業に携わったときには「これはすごい時代がやって来たな」と思いましたね。
佐々木:昔は編集者の仕事って夜中にやるのが普通だったのですが、それを利用すれば朝に仕事ができる。実際、最近は校閲を中国に外注している出版社って多いんですよ。時差はないですが、やはり単価が安い。
松井:単価の問題は大きいですよね。例えばコールセンター業務でいえば、米国の企業はインドで行っていることが多い。ですが、最近はフィリピンでも増えているようですね。ヒューレット・パッカード(HP)も中国にコールセンターがあって、そこで働く中国人をコントロールしているのは数人の日本人だと聞いたことがあります。
セコムという警備会社がありますよね。この会社もインドネシアでビジネスをやっていて、現地の警備員をコントロールしているのは2~3人の日本人。日本のローカルな警備会社ですらこういう形で対応しているんですよ。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング
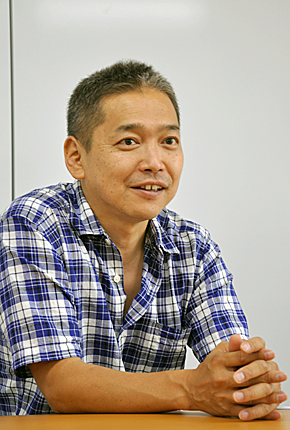 松井博氏
松井博氏