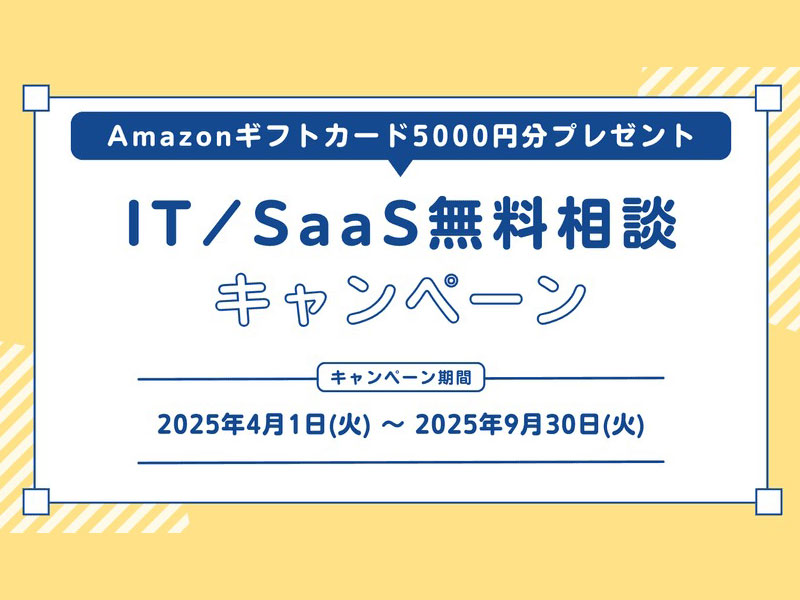- ITmedia ビジネスオンライン
- 潜在顧客は570万人!? 補聴器の普及の方策を考えてみた:それゆけ!...
潜在顧客は570万人!? 補聴器の普及の方策を考えてみた:それゆけ! カナモリさん(1/2 ページ)
それゆけ! カナモリさんとは?
グロービスで受講生に愛のムチをふるうマーケティング講師、金森努氏が森羅万象を切るコラム。街歩きや膨大な数の雑誌、書籍などから発掘したニュースを、経営理論と豊富な引き出しでひも解き、人情と感性で味付けする。そんな“金森ワールド”をご堪能下さい。
※本記事は、GLOBIS.JPにおいて、2012年6月22日に掲載されたものです。金森氏の最新の記事はGLOBIS.JPで読むことができます。
ここに1つのデータがある。2011年度の補聴器年間出荷台数48万8000台。この数字は、ここ数年横ばいという(日本補聴器工業界調べ)。
聴力に不自由を感じている人が増えていないなら、横ばいは結構なことだ。だが、年々難聴が増える環境にあるのも事実だ。
高齢者人口が増加していることに加え、例えば「音響騒音性難聴」患者の拡大。とりわけ大音量で長時間使用することにより起こる「イヤホン難聴」が近年、増えていると聞く。この結果、通常は40代ぐらいから低下する聴力が最近では20代から衰え始めているというのである。また、長時間のPC操作やストレス過多などに起因すると言われる「メニエール症候群」や「突発性難聴」など、感応性難聴の増加は筆者の周辺でも認められる。
潜在顧客は拡大していると思われるのに、市場規模は横ばい。これは、なぜなのだろう?
「目立たない」から「魅せる」へと価値観の転換が必要
「補聴器システムの在り方に関する研究・二年次報告-補聴器普及のシーズに関する調査」(補聴器システムの在り方研究会・著)によると、聴力が低下している人の推定人口は日本の総人口の約15.43%を占め、このうち「無自覚」な難聴者が47%、「『きこえ』に不自由を感じているものの、一度も補聴器を使用したことがない」人が29%に及ぶという。
自身が難聴であるという認識のない人については、検診機会を増やすなどの方策により、本人にとっては問題改善、メーカーにとっては市場拡大を見込める。
筆者が着眼したのは、「『きこえ』に不自由を感じているものの、一度も補聴器を使用したことがない」という回答の多さだ。ざっと概算して、570万人の人が不調を感じながらも、少なくとも補聴器という手段を改善策として選んでいないことになる。
金銭的な理由も1つにはあるだろう。簡易なものでも数万円、つけ心地や音声品質にこだわった高性能なものでは30万~50万円と、補聴器はまだまだ高額な医療機器であり、しかも、現在主流のデジタル補聴器は、購入前に専門の技能者による調整をはさまなければいけない面倒さもある。
ただ、それ以上に看過できないのが、補聴器装着への抵抗感なのではないかと筆者は推察している。とりわけ若い世代の難聴者の心理は想像してあまりある。筆者が幼少の時分はメガネですら、「がり勉」「老眼」などと冷やかしの対象になったものだ。
気になってさらに追いすがり、各社ホームページなどで訴求ポイントを確認してみると、案の定、基本的には「よく聴こえる×目立たない」ことをKBF((Key Buying Factor=購買要因)として示している。しかし「目立たない」といっても、「完全に見えない補聴器」を作ることはできない。その訴求には限界があるのではないだろうか。
ネガティブなイメージが試用を躊躇させ、普及の妨げになっている。つまり、人の購買に至る態度変容を表した「AMTUL」で言えば、A=Awareness(認知)→M=Memory(記憶)という段階までは進んでも、T=Trial(試用)で断絶し、U=Usage(日常使用)→L=Loyalty(手放せなくなる)という過程に進まない、と、類推される。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング